
「産休」と「育休」は似ているようでまったく違う制度です。
お恥ずかしながら、私も子どもを授かるまではまったく知らなかったです。
今回は「産休」と「育休」の違いについてご紹介いたします。
この記事はこのような方に向けて書いています。
- 「産休」「育休」の違いがいまいちよくわからない方
- 休業中にどれくらいのお金がもらえるか気になる方
- 部下へ「産休」「育休」の説明が必要な管理職の方
この記事をお読みいただくとこのようなことがわかります。
- 「産休」「育休」の言葉の意味や違いがわかる
- 休業中にどれくらいのお金がもらえるかがわかる

「産休」「育休」の記事や動画はたくさんあります。
この2つの違いがわかれば他の記事や動画の理解がとても進みます。
大枠はそれぞれすごくシンプルなので、ぜひ最後までお付き合いください。
「産休」と「育休」はここが違う
結論
産休・・・ママが対象。出産前 ”6週間” と出産後 “8週間” の休業。
育休・・・ママ、パパが対象。原則、子どもが1歳になるまでの休業。
「産休」とは、 ”産前・産後休業” のこと

「産休」とは、 “産前・産後休業” のことで、出産前 ”6週間” と出産後 “8週間” にママがとれる休業のことです。
「産休」は、労働基準法というお堅い法律で決められているので、働いていて妊娠しているママであればどなたでも取得することができます。
正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど、立場に関係なくどなたでも取得することができるんですね。
この会社では産休が取れるけど、この会社では取れない、ということはありません。

産休はパパは取得できません。
令和4年10月より、「産後パパ育休」という制度が新設されたのですが、これは育休制度のひとつですね。
出産手当金:どのような人がもらえるか
産休は立場に関係なく、妊娠している働くママならどなたでも取得できるとご紹介しました。
しかし、産前6週・産後8週の間にお金がもらえるかどうか、これは立場によって違います。
休めることと、お金がもらえることは別なんですね。

産休中にもらえるお金は「出産手当金」という名前です。
もらえる方、もらえない方はこのようなイメージです。
- 勤務先で健康保険に加入しているママ
基本的に健康保険に加入していれば「出産手当金」というお金が支給されます。
細かくみると、妊娠4カ月以降(85日以降)の出産でないと支給されなかったり、出産前後に退職が絡むとどいなの?というポイントはありますが、まずは「健康保険」に加入しているかどうかが最大のポイントになります。
健康保険に加入しているかどうかについては、毎月の給与から ”健康保険料” が引かれているかどうかを確認すればOKですね^^
- 国民健康保険に加入しているママ(自営業等)
- 家族の健康保険で扶養されているママ
- 産休中に出産手当金以外の給与のあるママ
自営業やフリーランスの方は ”健康保険” ではなく、 ”国民健康保険” という制度に加入しています。
とても残念なのですが、”国民健康保険” には出産手当金がありませんので、自営業や個人事業主の方は産休中に必要となるお金はご自身で準備しておく必要があります。
また、家族(一般的にはパパ)の扶養に入っているママにも出産手当金は支給されません。これはママに収入があるかどうかに関わらず、です。
加えて、産休中に給与が支払われる場合も支給されません。
出産手当金は出産に伴う収入の減少を補うためのものですので、産休中に給与が出る場合は収入の心配が無いので出ないことになっているんです。

日本には「産休中の給与を全額出しますよ!」という会社が存在します。
ただ、このような福利厚生のある会社は本当に極々一部ですので、基本的に産休中はお給料は出ないと考えてくださいね。

たまに、「休みながらお給料もらえて良いな〜」と言われる方がいますが、出産手当金はお給料ではありません。みなさまが払ってきた保険料(健康保険料)をベースに支給されるお金なので、当然の権利なんですね。
出産手当金:いくらもらえるか
結論
1日あたりの支給額・・・日給の2/3相当
この金額が98日分(産前6週+産後8週)支給されることになります。
ちなみに、1日あたりの支給額は2/3相当を言い換えると67%程度になりますが、出産手当金には社会保険料や税金がかからないので、実際は給料の80%程度が支給されると考えることもできますね^^
詳細な計算式はこのようになっています。
“支給開始日以前の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均額” ÷ 30日 × 2/3
ここまで理解するのはしんどいので、「日給の2/3くらいが98日分もらえるんだな〜」と押さえていただければOKです。
また、「出産手当金」には理論的には「これ以上は支給しないよ!」という上限額があるのですが、かなり高額なので無視して問題ありません。(毎月のお給料が135万以上の人とかの場合なので・・・)

双子などの多胎妊娠の場合は、98日(産前6週+産後8週)が154日(産前14週+産後8週)になります。多胎の場合は、ママの心身の負担がより大きいので ”産前” が長くなっているんですね。
「育休」とは、 ”育児休業” のこと

「育休」とは、 “育児休業” のことです。
働くパパ・ママが1歳未満の子どもを育てるために取れる休業のことですね。
「育休」は、”育児・介護休業法” という法律で決められているので、「産休」とは別に決められている制度です。

「産休」は労働基準法で定められていました。
「産休」はママの身体の保護、「育休」はパパママの育児と仕事の両立に注目しているイメージです。目的が違うので法律も違うんですね。
また、「産休」は正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど、立場に関係なくどなたでも取得することができましたが、「育休」には取得要件があります。
「私は取れたけど、契約社員の〇〇さんは取れなかった」ということが起こり得ます。
特になし
※ただし、会社と労働者で以下のような取り決めがある場合は、取れない可能性があります。
- 雇用された期間が1年未満の場合
- 1年(1歳以降の休業の場合は、6カ月)以内に雇用関係が終了する場合
- 週の所定労働日数が2日以下の場合
子どもが1歳6カ月になるまでに労働契約期間が満了しないこと
有期契約労働者の場合は、”復帰後すぐに契約終了にならない人” が対象になるイメージです。
育児休業給付金:どのような人がもらえるか
晴れて「育休」が取得できたとしても、やはり休めることとお金をもらえることは違います。
育休中にもらえるお金を「育児休業給付金」と言いますが、これがもらえる方、もらえない方はこのようなイメージです。
- 雇用保険に加入していて、保険料を支払っていること
- 原則1歳未満の子の養育のために育休を取得していること
- 育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上あること
- 育休中、各1カ月に休業開始前の賃金の80%以上が支払われていないこと
- 育休中の就業日数が各1カ月に10日以下または80時間以下であること
- 上記を満たさない方
読み飛ばしたくなる文量の要件ですが、実はそんなに複雑なことは書いていません。
大前提として、「育児休業給付金」をもらうには前提として雇用保険に入っていることが必要です。
「育児休業給付金」は会社が払うものではなく、雇用保険という制度から支払われるお金だからです。
雇用保険に加入しているかどうかについては、毎月の給与から ”雇用保険料” が引かれているかどうかを確認すればOKですね^^

ポイント!
「出産手当金」は「健康保険料」を払っているかどうか。
「育児休業給付金」は「雇用保険料」を払っているかどうか。
その他の要件については、
・「育休」をとっているかどうか
・育休中に給料をもらっていないか/働きすぎていないか
がポイントですので噛み砕けばとてもシンプルな要件なんです^^
育児休業給付金:いくらもらえるか
結論
半年間は給料の67%、その後は最長2歳になるまで給料の50%が支給されます。
計算式(一月あたりの支給額):日給×30日×67%(約半年以降は50%)

「育休」は期間が長いので1月あたりで計算します。
ちなみに「育児休業給付金」にも社会保険料や税金はかからないので、半年間は実質80%程度が支給されると考えることができますね。
また、「育児休業給付金」には上限額があります。
産休中の「出産手当金」では、ほぼ関係無かったのですが、「育児休業給付金」では関係してくる方がいらっしゃるかもしれません。
ざっくり45万円以上の給料をもらっている方は上限に引っかかってきますのでご注意ください。
(給付率67%) 支給上限額 305,319円 支給下限額 53,405円
(給付率50%) 支給上限額 227,850円 支給下限額 39,855円
※令和5年7月31日までの支給額。金額は毎年変わります。
最後に
「産休」と「育休」の違いについて大枠をご紹介させていただきました。
妊娠がわかったママ・パパは、これから赤ちゃんを迎えるためにいろいろなことを調べているところかと思います。
上司や人事部に相談する前に、まずは「産休」「育休」の概要を押さえてみてくださいね。
関係者に相談・報告する際にとてもスムーズに話が進むと思いますよ。

最後までお読みいただき本当にありがとうございました。
育休中のお金に関する内容は別記事でも書いています。
別記事:「育児休業」、休業中はいくらもらえる?期間はどれくらい?
別記事:【児童手当】子ども2人の場合、0円〜30000円/月までの幅があります。
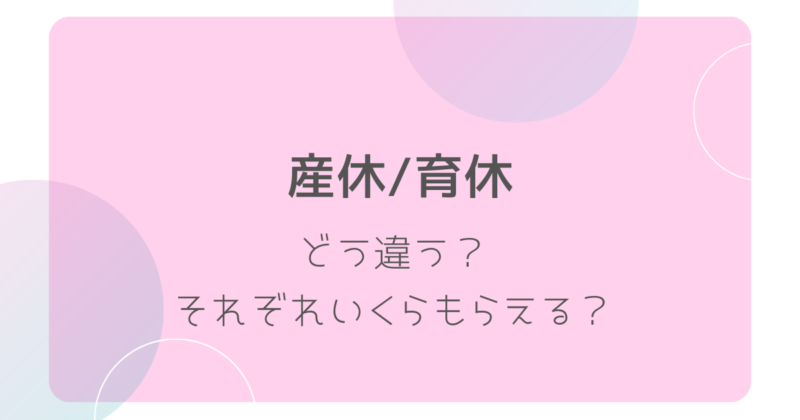
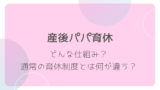
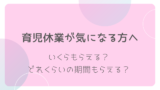

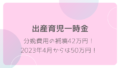
コメント